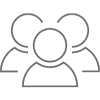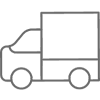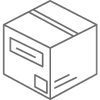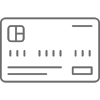【日本酒ペアリングの始め方】誰でもわかる基本と応用の理論を解説
ペアリングとは、料理とドリンクの組み合わせを工夫することで、より美味しい味わいをつくりだすことです。
ワインではよく用いられていた「ペアリング」の取り組みが、最近は日本酒でも取り入れられるようになっています。
「ペアリング」という言葉に敷居の高さを感じている方も多いかもしれませんが、難しく考える必要はありません。
唐揚げにビール、和菓子に緑茶、などの身近な組み合わせも、ペアリングの1つです。
ペアリングは確かな理論が確立しているわけではありませんが、現時点でわかっていることを中学生でもわかるように噛み砕いて整理しました。
この記事の内容を実践すれば、自宅や居酒屋で日本酒を何倍も美味しく楽しめるようになるはずです。
簡単な基本を抑えて、実生活に少しずつ取り入れるだけでも世界がまったく変わってきます。
世界一わかりやすい日本酒ペアリング理論

日本酒のペアリングについては色んな方々が論を展開されておられます。
色んな人の意見を目にしていると混乱しますが、それらにもやはり共通する部分があります。
意見が一致しているだけあって、その部分は自分で実践してみても「おっしゃるとおりだな」と納得できることばかりです。
そこで、日本酒ペアリングについて、現在わかっていることを整理し、理解も実践もしやすい「ステップ1〜5」の5つの段階で整理しました。
このステップは、「基礎→応用」「簡単→難しい」という順で並べられています。
また、数多くあるペアリングのテクニックをカテゴリごとに分類・整理し、1ステップ1カテゴリの形で整理することができたため、これまでにないレベルで理解しやすくなりました。
ステップ1から順に実践していけば、とてもスムーズに、楽しみながらペアリングの知識とテクニックを身につけられます。
ステップ1. まず「濃さ」を合わせるのが基本

まず第1に考えるべきは、料理と日本酒の「濃さ」を合わせることです。
ペアリングの基本の考え方にして、とても簡単に取り組めるポイントでもあります。
この点については日本酒造組合中央会をはじめ、多くの団体、有識者、料理人の方々が明言しており、日本酒業界の共通見解だとみていいでしょう。
味の濃い料理、こってりした料理には、濃いお酒、しっかりしたお酒。
薄味、さっぱりした料理には、軽快なお酒。
ということです。
淡白な白身魚のお刺身に、濃醇な純米酒を合わせてはお刺身の味が負けてしまいます。それよりは軽快な吟醸酒を合わせたほうが「よく合う」と感じられます。
逆もしかりで、脂の多いこってりとした料理に、水のようにすっきりしたお酒を合わせても日本酒の味が感じられなくなります。
「濃さ」は「濃淡」「重さ」「厚み」「ボリューム」「ボディ」などと置き換えても結構です。
もし、どんなお酒が濃いのか、または淡いのかがわからないという方は記事末の「日本酒の種類ごとのペアリング例」の項の表を参考にしてみてください。
余談ですが、日本酒は料理にとても合わせやすいお酒です。
よって、今述べたように「料理との濃さを合わせ」て、料理とお酒が喧嘩しないようにするだけでも、これから解説するペアリングが意図せずに起きることも多いです。
だから「濃さを合わせる」だけでも、料理と日本酒をぐっと美味しく楽しめるようになります。
ステップ2.さらに色んな要素を合わせる

ひと言で言えば「似たもの同士を合わせる」ということです。
フルーティーな日本酒には、似た香りのするフルーツを使った料理が合う、という話ですね。
「同調」「調和」などといわれ、やはり多くの著名人の方々も口をそろえる方法論でもあります。
合わせるポイントとしては、
- 香り
- テクスチャー
- 温度
などがあります。
基本的に、「美味しいもの」+「美味しいもの」が「美味しい」と感じるのは当然の話です。
しかし、相性が悪いと「美味しいもの」+「美味しいもの」が「イマイチ」になってしまいます。
「ではどうやってそのミスマッチを防ぐか」に役立つのが、「似たものを合わせる」という指針です。
「似ている部分」という接点があると、口の中で合わさった時もお互いのバランスを崩さずに味わいが調和することが多いです。
長くなるので理論は割愛しますが、これは経験からも感覚的に理解していただけると思います。
テクスチャーを合わせるというのは、例えば「とろみのある料理には、とろみのあるお酒を」ということです。
美味しくするためにとろみをつけているわけだから、さらさらの日本酒でそこに水をさすよりは、とろみのあるお酒で余計な邪魔をしないようにしたほうがいいという方法論。
温度もポイントの1つで、温かい鍋やおでんには、温めたぬる燗がとてもよく合います。
キーワードは「接点」です。
ステップ3.弱点を補完する

お互いの足りない要素を補完したり、料理のネガティブな部分をカバーするという方法です。
五味の完成
料理とお酒を組み合わせて、基本味といわれる甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の5つの味を揃えるという考え方です。
日本酒に、塩気の強いたくあん漬けなどが合うのもこの理屈です(日本酒には塩分がなく、たくあんの塩気で五味が完成したことで美味しく感じられる)。
もちろん、日本酒で料理の五味を補完するという考え方もできます。
「旨味」「甘味」「酸味」「苦味」のどれを補完したいかを考え、その味が強い日本酒を合わせていきます。
香りの付加
日本酒の香気成分で料理の味わいに華を添える方法です。
例えば、淡白な白身魚のお刺身に、フルーティーな吟醸香の日本酒はよく合います。
これは、すでに「フルーツを使った白身魚のカルパッチョ」が料理として定着していることからも想像に難くないと思います。
「この料理にはどんな薬味を入れれば美味しくなるか」と同じような考え方で日本酒を合わせていくとうまくいきやすいです。
余韻を長くする
西麻布の日本酒バー「EUREKA!」の千葉麻里絵さんが言及されている方法論。
「料理に含まれるアミノ酸を日本酒のアミノ酸と合わせることで、日本酒の余韻を長く楽しむことを可能とするペアリング」
マスキング
原料に麹を使用する日本酒には、魚介や海藻料理の生臭みを抑える効果があります。
これは鼻腔上の魚の生臭さを感知する部分(受容体)に日本酒の香気成分が収まることで生臭さを感じなくするためだといわれています。
数あるお酒の中でも特に日本酒に特徴的な点で、魚介料理にも臆せずペアリングさせることができます。
ウォッシュ効果
「肉料理に赤ワイン」に代表されるように、アルコールや渋味成分(タンニン)で料理の油脂成分を洗い流し、すっきりさせることです。
基本的に日本酒にはタンニンは少ないですが、樽由来のタンニンを持つ樽酒はウォッシュ効果が高く、肉料理やうなぎ料理などとの相性がいいです。
ステップ4.あえて似てないもの同士で

ここからは上級者向けです。
濃淡や香りなど、「似た者同士」を合わせるのが基本だとお伝えしましたが、その基本をあえて崩します。
似ていないもの同士を組み合わせることで、食体験のいち部分を際立たせます。
西麻布の日本酒バー「EUREKA!」の千葉麻里絵さんが提唱する以下の2つの方法論がこのステップに該当します。
対照的なもの同士:異なる五味やフレーバーが特徴的な料理と日本酒を合わせることでメリハリをつけインパクトのあるペアリングに仕上げる
陰影をつける:日本酒をコントラストとして用いて、料理をさらに味わい深いものにするペアリング
前述のとおり、似てないもの同士を組み合わせるとバランスが崩れて「イマイチ」に感じられることが多いため、美味しい組み合わせを見つける難易度は上がってきます。
基本のペアリングに慣れてきたら挑戦してみるのもいいかもしれません。
ステップ5.マリアージュを目指す

ここまでは、味わいを「足し合わせる」「目立たせる」という発想でペアリングをしてきました。
しかし最後は、料理とお酒を組み合わせることで、まったく新しい”第3の味”を「生み出す」ことを目指します。
ワインの世界でマリアージュと呼ばれるもので、「油脂成分の多いフォアグラと極甘口ワイン」などの組み合わせが代表的です。
西麻布の日本酒バー「EUREKA!」の千葉麻里絵さんが提唱する以下の2つの方法論がこのステップに該当します。
記憶にある香味の再構築:料理と日本酒を合わせることで、双方に含まれない、しかし感じたことのあるあの味を生み出すペアリング
新たな香味を生み出す:料理と日本酒を合わせることで、全く新しい香味を表現するペアリング
両者の違いは、前者は「プリンに醤油をかけたらウニの味になった」のようなイメージ。
後者は「料理と日本酒の組み合わせで既存の食品では例えられない新しい美味しさが生まれる」とイメージされるといいでしょう。
「記憶にある香味の再構築」については、もしかしたらご本人はマリアージュだと認識されてないかもしれませんが、「単純な足し算ではない、第3の味を生み出すペアリング」という点でこちらに分類されるものだと考えます。
番外編:頭を使わなくていいペアリング

ステップ1の「濃さを合わせる」はかなり簡単に実践できますが、それでもハードルを感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、細かいことを一切考えずにできるペアリングをご紹介します。
地域を合わせる
地酒はその地域の食文化に根ざし、郷土の食材や料理に合うように酒造りされています。
よって、食材の産地、その地域の郷土料理と地酒を合わせれば自然とペアリングがうまくいくことが多いです。
発酵食品と合わせる
発酵によってつくられた日本酒は、同じく発酵でつくられたしょうゆや味噌、チーズなどと相性がいいです。
これらの調味料を使えば、食材と日本酒の接点ができ、調和のペアリングのきっかけとなります。
塩気の強いものと合わせる
「五味の補完」でも言及しましたが、日本酒にほとんど含まれないのが塩味。塩をつまみに日本酒が飲めると言われるのはこのためです。
ですので、たくあん漬けなどの「塩気が強くかつシンプルなつまみ・料理」はほとんどの日本酒に合うはずです。
相性が悪い例
利酒師養成のテキスト『日本酒の基』では、日本酒と料理の相性が悪いパターンを次の3つに分類して紹介しています。
平行
料理と日本酒を合わせても、プラスの効果が何も感じられない組み合わせです。
「調和」を引き出すために、料理と日本酒の共通性をもう少し意識すると改善するかもしれません。
反発
料理単独、または日本酒単独では感じない不快な香味が生じたり、強調されること。
ワインの「白ワインとカズノコ」などが有名です。
アンバランス
ステップ1の「濃さを合わせる」がうまくいってないケースのことです(牛カルビに繊細な吟醸酒を合わせるなど)。
また、STEP1〜2で、「似た者同士を合わせる」とありましたが、例外的に「強い五味」同士は、合わせるとその味が強調されすぎてバッドペアリングになりやすいです。
(甘味の強い料理に甘味の強いお酒、酸味の強い料理に酸味の強いお酒、など)
「濃さ」を合わせるというには、あくまで全体の「厚み」「重さ」を合わせるということであり、必ずしも五味を合わせるわけではない点にご注意ください。
日本酒の種類ごとのペアリング例

日本酒の特徴ごとに、ペアリングしやすい料理の特徴を表にまとめました。
飲んだことのないお酒を料理とペアリングするときの大まかな指標になると思います。
表の2列目のラベル分類は傾向としてその特徴に該当するお酒が多いということであり、必ずしもここに分類されるわけではないという点にご注意ください。
(表では純米酒は醇酒に分類されているが、爽酒や薫酒に該当する純米酒もある。)
SSIの提唱する香味特性別分類を参考に分類しています。ペアリングの例は「同調」をベースにしたものがほとんどです。
| 香味特性別分類 | ラベル分類 | 合う料理の特徴 | 具体例 |
| 爽酒 軽快でなめらか |
本醸造酒 純米吟醸酒 普通酒 生酒 |
シンプルな味付けの料理 | 冷奴 刺し身 寄せ鍋 おでん サンマの塩焼き 牛たんの塩焼き |
| 薫酒 香りが高い |
吟醸酒 大吟醸酒 純米大吟醸酒 |
・爽酒に合うものの中で華やか・フルーティーな香りが良いアクセントになるような食材・料理 ・香り高い調味がされた料理 |
白身魚の刺し身 蒸し鶏 サラダ・フルーツ 魚介と香草のマリネ |
| 醇酒 コクがある |
純米酒 生酛造 山廃 |
・しっかりした味付けの料理 ・旨味やコクの強い料理 |
ぶり大根 酢豚 焼き鳥 牛肉のステーキ もつ鍋 |
| 熟酒 熟成タイプ |
古酒 | 濃い味付けで油脂も多い料理 複雑で重厚な香味の料理 熟成した醤油や味噌を用いた料理 粘性のある料理 スパイスを効かせた料理 |
豚の角煮 すき焼き 鴨のロースト 牛肉のオイスターソース炒め 熟成したチーズ 羊羹・チョコレート ドライフルーツとナッツのケーキ |
SSI提唱の香味特性別分類より